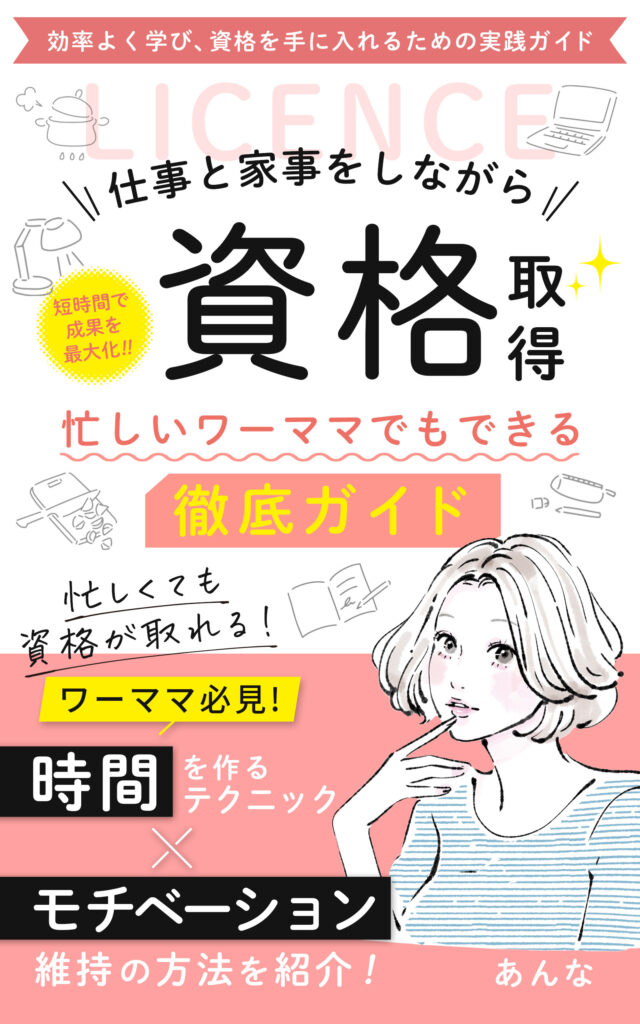公務員を辞める決断は、家族や将来設計、経済的な安定を含めた大きな賭けに似ています。
私自身、安定した待遇を捨てて民間に転職しましたが、結果として後悔はありません。
ここでは「なぜ後悔しなかったのか」を私の体験を交えつつ、同じ選択を考えている人が後悔を減らせるように、具体的な準備と考え方を詳しくまとめます。
なぜ公務員を辞めると後悔する人がいるのか

まず、後悔が生まれる典型的な要因を整理します。これを理解すると、同じ失敗を避けやすくなります。
- 準備不足:退職後の収支計画や再就職プランが曖昧。収入が途切れたときに不安が大きくなる。
- 市場価値の過小評価:公務員で培ったスキルが民間でどれだけ評価されるかを見誤る。
- メンタル面の変化:求められる成果主義やスピード感に慣れず、自己効力感が下がる。
- 社会的・家族的プレッシャー:周囲の理解が得られず孤立感を覚える。
- 手続きや制度の落とし穴:年金・健康保険・住民税などの切り替えタイミングを知らずに困る。
私が後悔しなかった核となる要素
私が「後悔しなかった」と言える理由は、感情だけで決めず、段階的に準備して実験しながら踏み切ったからです。ポイントは次の4つです。
- 具体的な資金計画(最長12〜18か月の生活費を確保)
- 転職市場での自分の相対的価値を事前に検証(面談・副業・派遣経験)
- スキルを増やすための行動(資格・オンライン学習・プロジェクト経験)
- 心理的なリスク管理(家族への説明・メンターや仲間づくり)
退職前にやるべき現実的なチェックリスト

以下は私が実際に踏んだステップを、退職前の推奨タイムラインに沿って整理したものです。時間や状況に応じて調整してください。
- 「なぜ辞めたいのか」を紙に書き出す(動機の明確化)。感情と合理的理由に分ける。
- 家族と早めに相談。ライフプラン(住宅ローン、子どもの教育費など)を共有する。
- 貯蓄目標を設定:生活費×12〜18か月+想定転職活動費(移住費用など)。
- 副業や兼業で小さくトライし、民間の仕事感覚を掴む(ブログ、フリーランス案件、週末業務)。
- 市場リサーチ:転職エージェントに登録、複数社と面談して自分の市場価値を確認。
- 必要なスキル/資格を洗い出し、学習計画を立てる(週5〜10時間の学習時間を確保)。
- 履歴書・職務経歴書をブラッシュアップ。ポートフォリオ(成果物やプロジェクトの記録)を作る。
- 可能ならうまくいけば内定を得るまで有給消化で徐々にシフト。
- 実務的な準備:離職後の健康保険、年金(国民年金)への切替方法を確認。
- 退職金の見積もりと税・社会保険のシミュレーションを行う。
- 転職活動を本格化。面接練習、想定質問の用意、年収交渉の戦略作り。
- 家賃や住居に関する計画(引っ越しや住替えがある場合のコスト見積もり)。
- 退職届の提出と退職日までの業務引継ぎを明確にする。
- 離職票や必要書類の確認(雇用保険、年金手続き関係)。
- 精神的な整理:やることリストと連絡先を家族と共有する。
スキルとキャリア戦略
公務員を退職した後にどのようなキャリアを歩むのかを明確にしておくことで、その後の戦略が立てやすくなります。
- IT系:プログラミング、データ分析(Python、SQL)、IT系資格(AWS、GCPなど)。
- ビジネス系:簿記、マーケティング、プロジェクトマネジメント(PMPに近い勉強)。
- 公共経験の活かし方:契約管理、規制対応、行政系プロジェクトの経験は民間のコンプライアンス・CSR部門で重宝される。職務の成果は数値やプロセス改善として見える化する。
私は公務員時代の健康保険・年金の経験を活かし、社会保険労務士の資格を取得し、転職しました。難関資格を持っていると、転職ではかなり有利となりますのでおすすめです。
誰かに相談しながら自己分析を進めたい…
プロのキャリアコーチがサポートしてくれるマジキャリ
エージェントと違い、求人紹介や転職決定で弊社が金銭を頂くことはありません。そのためマジキャリでは、短期的な転職だけを目的とせず、対話を重ねてあなたの潜在的なお悩みや志向性、軸を引き出します。
https://career-meet.com/より引用
強制されたり周りに左右されるのではなく、あなただけの「軸」をもとに、自分らしいと思えるキャリア選択のお手伝いをします。
サービス自体は有料ですが、初めての方は1時間の無料カウンセリングを受けることができます。そして、無料体験をされた方限定で自己分析シートをもらうことができます。
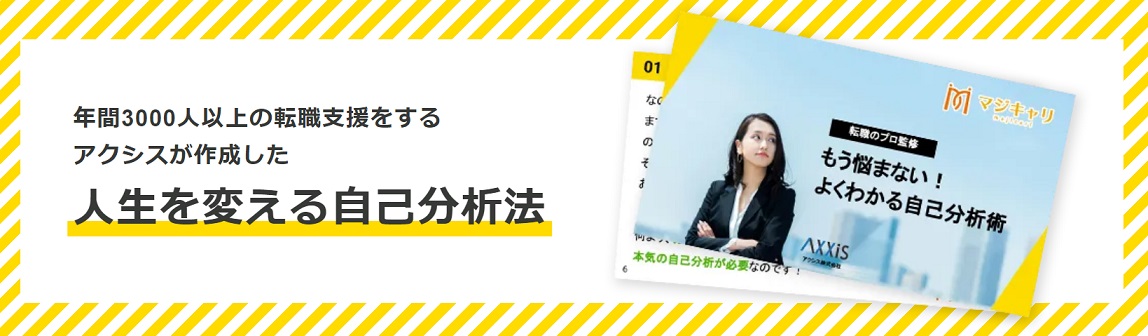
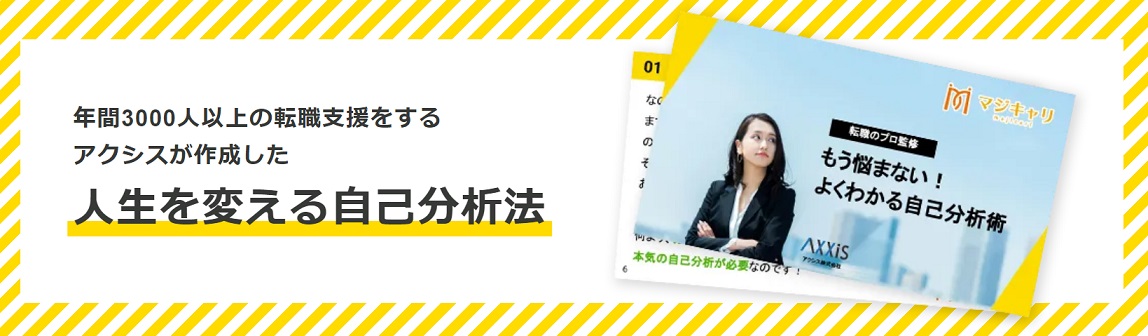
自己分析には客観的な視点も取り入れることで、より深く自己の理解を深めることができるようになります。まずはこういった無料のサービスを活用し、今後のキャリアについて考えてみるのがおすすめです。
転職先の選択肢とそれぞれのメリット・注意点


ここからは、転職先の選択肢と、それぞれのメリット・デメリットについて解説していきます。
民間企業(事務・管理職)
企業の事務・管理職は「給与の伸びしろ」が特に魅力です。
年功序列が残る企業でも成果主義を導入する動きが強まり、成果を明確に示せれば年収上昇のチャンスはある一方で、評価基準の変化に柔軟に対応することが求められます。
具体的には、KPIの設定やデータで説明できる実績、部門間調整力、プロジェクトマネジメントの経験が評価に直結します。
また、管理職になると人事評価や予算配分、コンプライアンス対応など責任範囲が広がるため、リーダーシップや労務管理の基礎知識が必要です。
ワークライフバランスは業界や企業文化次第で大きく変わるため、業務量だけでなく有給取得の現実性やテレワーク制度の運用実態も確認すべきポイントです。
公務員ほどではありませんが、身分が安定するのも大きなメリットです。
ベンチャー/スタートアップ
ベンチャーは大きな裁量と急速な成長機会を与えてくれます。少数精鋭の環境では意思決定の速さや幅広い業務経験が得られ、短期間でスキルセットを拡張できます。
ただし、事業の不確実性、資金調達の成功可否、創業メンバー以外の報酬構造(株式のバイバックやバリュエーション)など、経済的・制度的なリスクも高いです。働き方はフラットですが労働時間は長くなりがちで、燃え尽きやすい面もあります。
リスクを抑えるには、入社前に資金繰り(ランウェイ)、株式やストックオプションの条件、役割の明確化、退職・買戻し条項の確認を行うと良いでしょう。キャリアの出口戦略(M&A後の扱い、上場後のロックアップ解除など)も考慮しておくと安全です。
コンサル/シンクタンク
コンサルタントやシンクタンクは、専門性を磨きながら短時間で多様な業界知識を蓄積できる職種です。クライアント問題の本質を捉える分析力、提案力、プレゼンテーション能力が求められ、これらはどの企業に転職しても高く評価されます。
反面、プロジェクトベースでの納期拘束、出張や長時間労働、成果に対する高い期待が精神的負荷を生むことがあります。働き方改革やプロジェクトのアウティング(外注)を活用している企業も増えていますが、体力的・精神的マネジメントができるかが鍵です。
将来的に事業会社の経営企画や事業開発へ移る道も開けます。専門分野の学位や認定資格(例:MBA、特定業界の資格)があるとポストの幅が広がります。
フリーランス/起業
フリーランスや起業は自由度が高く、働く時間や取り組むプロジェクトを自ら決められます。高単価案件やビジネスの成功があれば収入は飛躍的に増える可能性があります。
ただし、業務の不安定さ、営業・請求・税務といったバックオフィス作業、社会保険や年金の自己管理など、すべて自分で担う必要があります。
リスクを軽減するためのポイントは、顧客の分散化、契約書による支払い条件の明確化、常時の営業チャネル確保、短期の貯金目標(生活費の6カ月分など)です。また、個人事業主としての税務最適化や法人化のタイミングも重要です。
起業するなら、事業計画、最小限のプロダクトで市場を検証するMVP、市場規模・競合分析を早期に行うことが成功確率を高めます。
リスクは大きいですが、大きく成功することも。
5) 一度休職・留学
休職や留学は、燃え尽き症候群の回復、新たなスキル習得、視野拡大には非常に効果的です。
長期的なキャリア戦略を見直す時間や語学・専門知識の習得に集中でき、結果として復職後の市場価値を高めることも可能です。
一方で、収入が途絶える、社会保険・年金の扱いが変わる、職歴のブランクを履歴書でどう説明するかといった課題があります。
これを緩和する手段としては、休職中に短期契約やフリーランス業務で収入を補う、留学先やプログラムの選定時に奨学金や生活費の現実的な見積もりを立てる、帰国後の再就職プラン(企業との復職合意や同業界のネットワーキング)を事前に作ることが有効です。また、ブランク期間に得た成果(修了証、プロジェクト、資格)を定量的に示せるように整理しておくと再就職時に評価されやすいです。
心理面・人間関係のケア
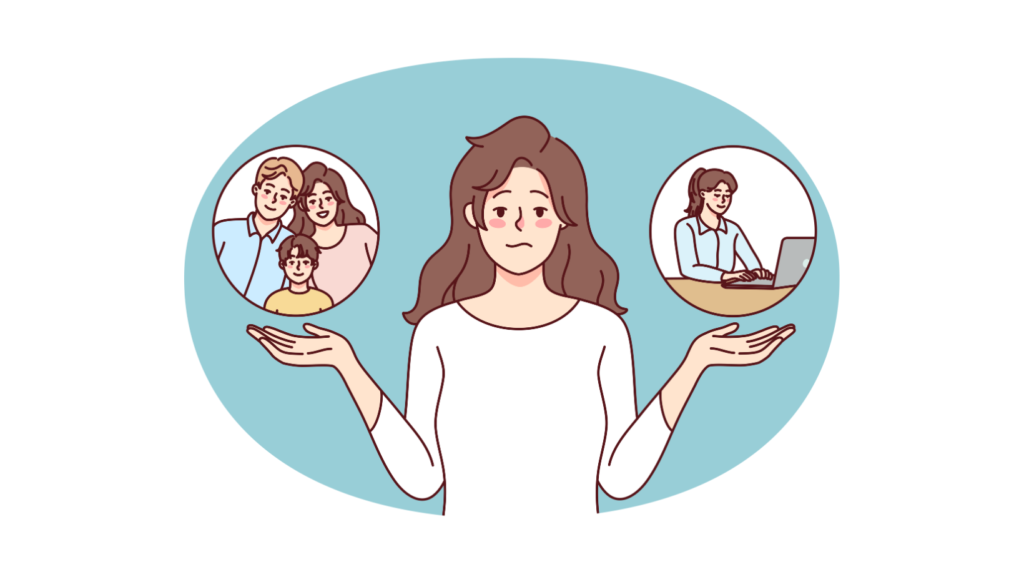
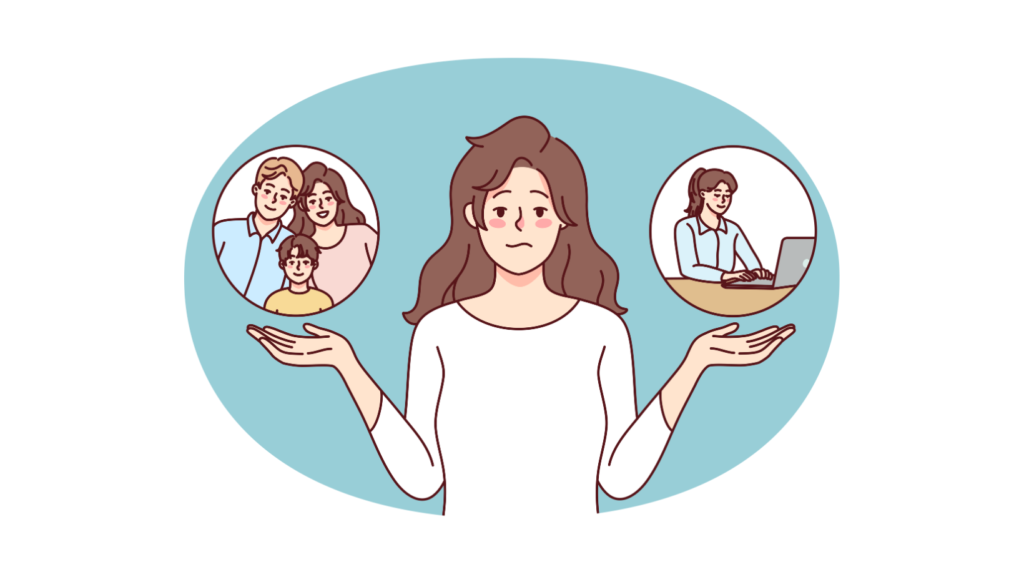
周囲に説明する際は「未来の選択」として伝える
公務員を辞めるとき、意外と大変なのが周囲の人を説得すること。私も、夫に「公務員を辞めるなんて勿体ない」とかなり反対されました。
ですが、そこで強行してしまうと味方であるはずの家族が敵になってしまいます。
周囲に説明する際は「未来に向けた選択」として話し、単なる思いつきでないことを示すために計画書やスケジュール、目標値や代替案といった根拠を添えると安心感が高まり、納得してもらえます。(例:6か月のロードマップや想定コスト、想定リスクとその対策)。
旧職場の人間関係を完全に断たない
旧職場の人間関係は完全に断ち切らずに適度な距離を保つのが得策です。
OB/OGや元同僚は情報源や紹介、メンターになる可能性を秘めています。定期的な近況連絡や業界イベントでの接点、SNSでの緩やかなつながりを残しておくのがおすすめですが、境界線は明確にしておきましょう。
完璧を求めすぎない
失敗を恐れず学びに変える姿勢を日常に組み込み、完璧を求めすぎない工夫をしましょう(小さな実験を繰り返す、振り返りノートをつける、MVPで検証するなど)。
感情的な落ち込みには短い振り返りと次の行動計画をセットにして回復を早めると効果的ですよ。
最後に:後悔を小さくするために意識すべきこと
決断そのものが正解かどうかは、数年経たないと分からないこともあります。
それでも後悔を最小化するために私が勧めたいのは「逃げの決断にしないこと」と「検証可能な計画」を組むことです。
小さく試し、学び、調整する。資金と情報を持ち、家族や専門家の意見を取り入れながら進めることで、辞めた後の不安はかなり和らぎます。
実際に私も公務員を辞めて民間企業に勤めていますが、ほとんど後悔することなく、ワークライフバランスを保ちながら働けているなと感じています。
後悔が少なくなるよう、計画的な退職、転職活動をおすすめします。